ServiceNow Knowledge 2025 イベントレポート:AIが主役の年次カンファレンス
導入:Knowledge 2025で「AIを仕事に活かす」

ServiceNow Knowledge 2025 会場の様子。参加者の熱気と盛り上がりが伝わってきます。
2025年5月、ラスベガスで開催された「ServiceNow Knowledge 2025」は、世界中から約25,000人もの参加者が集まる大規模イベントとなりました。
サービスナウ(ServiceNow)の年次カンファレンスである本イベントは、単なるITサービス管理の枠を超え、生成AIや自動化による業務変革が大きなテーマとなりました。基調講演に登壇したサービスナウCEOのビル・マクダーモット氏は「AIは21世紀における最大のチャンス」と位置づけ、2030年までに世界で22兆ドル規模の価値を生み出す潜在力があると強調しました。
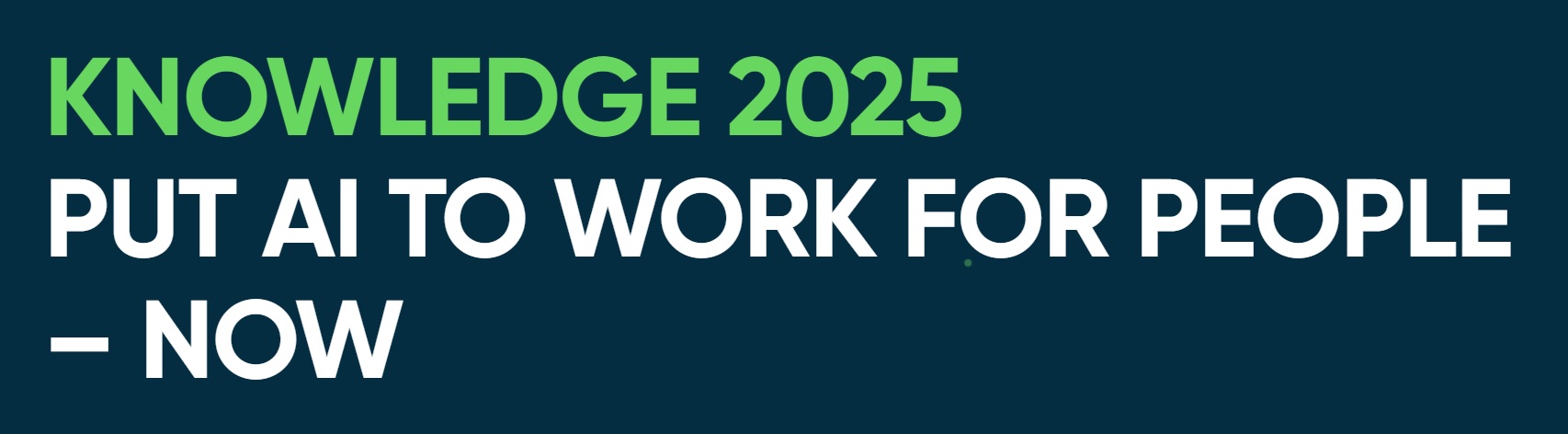
さらに「今こそAIを人々のために活用すべき時だ」(PUT AI TO WORK FOR PEOPLE – NOW)と述べ、ServiceNowが持つ単一プラットフォームの強みを活かして企業変革をリードしていく決意を示しています
今回のKnowledge 2025では、「あらゆるAI、あらゆるエージェント、あらゆるモデルを企業内で機能させる」ことを目指したServiceNow AIプラットフォームが披露されました。
また「AI時代に向けCRMを再定義する」という大胆な発表も行われ、従来型CRM(顧客関係管理)に代わるAIファーストの統合プラットフォーム戦略が示されています。
このように、Knowledge 2025はServiceNowが“AIプラットフォームによるビジネス変革企業”へ舵を切ったことを内外に印象付ける場となりました。
本記事では、Knowledge 2025で発表された主要な新機能やアップデート、注目セッションの内容を詳しく整理します。さらに、これら発表から読み取れるServiceNowの業界での位置づけと今後の方向性、そして明らかになった製品ロードマップ(将来のリリース計画やAI統合戦略)について考察します。最後に、これからServiceNow導入を検討する企業も、既にServiceNowを活用中の企業も、それぞれに役立つ示唆や活用のヒントをまとめます。AI時代におけるServiceNowの最新知見を、本イベント参加者の熱気あふれる声とともに臨場感たっぷりにお届けします。
「基調講演からずっとAIの話題一色!#Knowledge2025 に参加して正解だった🔥」 – 会場参加者のコメント (X)
新機能解説:Knowledge 2025で発表されたServiceNowのAI新機能

企業内でAIエージェントが活躍するイメージ。ServiceNowは統合プラットフォーム上で多数のAIエージェントが協働できる基盤を提供。
Knowledge 2025で最も話題を集めたのは、AIを核としたServiceNowプラットフォームの新機能群です。ServiceNowは今回、企業内のあらゆる業務にAIを浸透させるための包括的な基盤「ServiceNow AI Platform」を発表しました。これは、AI・データ・ワークフローを単一の土台に統合し、「Any Industry、Any Workflow、Any AI、Any Data、Any Cloud、Any System」――つまりどんな業種・業務・AIモデル・データソース・クラウド・システムでも受け入れるオープンで拡張性の高いプラットフォームを目指しています。これにより企業は様々なAI技術を自社のワークフローにシームレスに組み込むことが可能になります。
このAIプラットフォームの柱となる新機能として、以下が発表されました。
- AIエージェント:ServiceNowは既に数千もの「AIエージェント」と呼ばれる自律型ソフトウェア部品を用意しています。これらは従来のチャットボットを超え、ユーザの要求に応じて**自律的にタスクを実行**できる高度なAIです。例えば、ITサポート用のエージェントはインシデントの自動対応や対話的な問題解決を行い、運用管理用エージェントはアラートのトリアージ(優先度付け)や原因分析を自動で実施します。AIエージェントは部門ごと(IT運用、資産管理、プロジェクト管理、セキュリティ対応など)に用意され、業務の自己修復(セルフヒーリング)や自己防御を実現することで、人間の担当者がより付加価値の高い業務に専念できるよう支援します。
- AIコントロールタワー:大量のAIエージェントやAIモデルを導入すると、統制や管理が課題となります。そこで登場したのが「AI Control Tower(AIコントロールタワー)」です。これは企業内外のあらゆるAIアセット(エージェント、機械学習モデル、ワークフロー)を一元管理・監視・最適化する統合コックピットです。単一の画面から、AIの稼働状況やインベントリ、リスク&コンプライアンス状況まで把握でき、AI利用のガバナンスを徹底できます。ServiceNowのプラットフォーム内に組み込まれているため、他社製AIであっても安全に接続され、企業基準のセキュリティとガードレールの下で運用できます。例えば、AIモデルの利用状況に応じて承認フローを設定したり、不適切な動作が検知された際には自動でアラートを上げたりといった統制機能を備えています。
- AIエージェントファブリック:複数のAIエージェントが互いに連携し合うための「AI Agent Fabric(AIエージェントの織物)」も発表されました。これはServiceNowが提唱するエンタープライズAIエージェント同士の通信バックボーンで、各種AIが共通プロトコル(MCP: Model Context ProtocolやA2A: Agent-to-Agentプロトコルなど)でやり取りする仕組みです。要するに、ServiceNow製とサードパーティ製のエージェントがリアルタイムに情報共有・協調動作できるよう標準化された土台です。例えば、あるエージェントが顧客からの問い合わせ内容を分析し、別のエージェントに適切な処理を依頼するといった相互連携が可能になります。AIエージェントスタジオを使えば自社専用のエージェントを作成でき、AdobeやCisco、Microsoftなど主要パートナー企業のエージェントともマーケットプレイス経由で接続できます。このAIエージェントファブリックは現在一部早期利用者に提供中で、2025年第3四半期に一般提供開始予定です。
- ワークフローデータネットワーク:AIを賢く働かせるには、社内外の様々なデータにアクセスする必要があります。そこで発表されたのが「Workflow Data Network(ワークフロー・データ・ネットワーク)」です。これは100以上のデータソースに対応したデータ連携エコシステムで、構造化・非構造化データ、リアルタイム・過去データ、社内データ・サードパーティデータまで幅広く統合します。Amazon RedshiftやSnowflake、Databricks、BigQueryなど主要なデータベース・データレイクと直接接続し、データをコピーすることなくAIが利用可能にする「ノーコピー」統合が特徴です。Adobe、Boomi、Microsoft、Oracleといったパートナーとも協業し、業務アプリとの連携テンプレートも提供されています。これにより、ServiceNow AIプラットフォーム上で必要なデータが常にタイムリーに利用でき、AIエージェントが組織横断の情報に基づいて賢く判断・行動できるようになります。
- Autonomous IT(自律型IT運用):IT部門向けには、AIで高度に自動化された「自律型IT」機能が拡充されました。これは前述のAIエージェント群を活用して、ITサービス管理 (ITSM)、IT運用管理 (ITOM)、IT資産管理 (ITAM)、プロジェクト&ポートフォリオ管理 (SPM) などの領域で、人手を介さずにシステムが自己対応する仕組みを整えるものです。例えば、ITOM向けエージェントは障害アラートを自動で優先度付けし、原因分析まで行います。ITAMエージェントは必要なソフトウェアを自律的に調達し、ライセンス違反がないよう監視します。セキュリティ分野でも新たなAIエージェントが導入され、脅威インテリジェンスの収集からインシデントの封じ込めまで一連を自動化しました。Dave Wright氏(ServiceNow最高イノベーション責任者)は「これら新しいAIエージェントにより、システムが自己修復・自己防御する真の意味でのエージェンティックAI(主体的AI)が実現する」と述べています。つまり、人間の介入を待たずに問題を解決し、ITチームはより戦略的な仕事に集中できるようになるわけです。
- 次世代CRM(顧客管理)の強化:Knowledge 2025では、ServiceNowが従来強みとしてきたIT分野を超えて、CRM領域への本格参入を印象付けました。2024年末頃から「ServiceNowがSalesforceに挑む」という噂が業界で話題になっていましたが、今回その噂を裏付けるようにAIを駆使した新しいCRM機能が多数発表されました。ServiceNowのCRMは営業支援、オーダー管理、フィールドサービス、カスタマーサービス管理 (CSM) を一つのプラットフォームでカバーし、顧客体験を端から端までつなぐことを目指しています。
従来のCRMシステムが主に「営業(セールス)」に焦点を当てがちだったのに対し、ServiceNowは顧客との関係全体に寄り添おうとしています。ServiceNowでCRMを担当するテレンス・チェシャー氏は「従来のCRMベンダーは声高に”360度の顧客ビュー”や”オムニチャネル対応”を謳ってきたが、実際には販売の一部しかカバーできず、肝心の顧客体験を大きく改善するには至らなかった」と指摘します。ServiceNowは営業(セールス)だけでなく、受注後のサービス提供やサポートまで一貫した体験を提供することで、顧客満足度を劇的に向上させる狙いです。例えば、ある商品の契約から納品、アフターサポート、追加注文に至るまで、顧客が関わる一連のプロセスを一つのプラットフォーム上で追跡・自動化し、部門間の情報断絶をなくします。さらに生成AIや自然言語UIを活用して、現場のエージェント(オペレーター)やお客様自身がスムーズに問題解決できる仕組みも組み込まれています。
「ServiceNowの新CRM、営業からサービスまで全部入りで凄い。Salesforceもうかうかしてられないかも?🤔 #Know25 #CRM」 – Xより
このCRM強化に関連して注目すべきは、ServiceNowが2023年末〜2024年初頭にかけて行った大型買収です。AIプラットフォーム企業であるMoveworks社を約28.5億ドル(日本円で数千億円規模)で買収したニュースは業界を驚かせましたが、これはServiceNowがAIを駆使してCRMを再定義するための布石と見られています。実際、Knowledge 2025で披露された新CRM機能の多くに、Moveworksの持つ対話型AIや自然言語処理技術が活かされていると考えられます。
また、基調講演ではNVIDIA社との提携強化も発表されました。ServiceNowはNVIDIAと共同で高性能な大規模言語モデル(LLM)を開発し、その成果として「Apriel Nemotron 15B」というオープンソースLLMを披露しました。150億パラメータから成るこのモデルは、ルールの適用やゴールの重み付けを行いながら結論を導く推論能力に優れ、エンタープライズ向けに最適化されています。NVIDIAの最新GPU上で高速・効率的に動作し、リアルタイムなワークフロー実行を可能にするとのことです。2025年第2四半期中にこのモデルが利用可能になる予定で、ServiceNowプラットフォーム上でのAIの知能強化に寄与すると期待されています。
総じて、Knowledge 2025で発表された新機能群は、ServiceNowが「あらゆる業務領域をカバーするAIプラットフォーム」へと進化しつつあることを示しています。ITサービス管理から始まったServiceNowは、今やCRMや財務・人事など企業の基幹業務まで包含し、そこにAIの力を全面的に取り入れることで他社との差別化を図っています。こうした機能強化により、企業は単なる業務効率化に留まらず、ビジネスそのものの変革(トランスフォーメーション)を推進できるでしょう。
「ServiceNowヤバい、新しいAIプラットフォームで社内の全部署が一気通貫に…未来来たな✨ #ServiceNow #AI #DX」 – Xより
注目セッション:基調講演とイベントハイライト

Knowledge 2025 Day 1 Mainstage Keynote。左からNVIDIA CEO、ServiceNow CEO。
Knowledge 2025の初日は、ServiceNow会長 兼 CEOのビル・マクダーモット氏によるオープニング基調講演で幕を開けました。マクダーモット氏は「今こそAIを人々のために活用すべき時代である」と力強く訴え、前述した数々の新発表(AIプラットフォームやAIエージェント群)を自ら紹介しました。基調講演には特別ゲストとして、NVIDIAの創業者 兼 CEOのジェンスン・フアン氏が登壇し、AIがビジネスの未来をどう変えていくかについて対談しました。また、AstraZeneca社のCDIO(最高デジタル情報責任者)であるシンディ・フーツ氏もステージに登場し、医薬業界におけるAI活用の可能性について語りました。まさに産業の枠を超えたリーダーたちが一堂に会し、「AIのフルポテンシャルを解き放つ」というビジョンを共有したのです。
2日目の朝には、ServiceNow社 長 兼 CPO/COOのアミット・ザヴェリ氏による基調講演が行われました。ザヴェリ氏のセッションでは、「約束されたAIユートピアはどこにあるのか?」という問いかけのもと、現実世界でAIがどのように仕事を変革しているかが議論されました。顧客企業の事例紹介も交えながら、ServiceNowがAI・データ・ワークフローを単一プラットフォームで統合し、スピードとスケール、確実な成果をもたらしていることが示されました。具体的には、ある金融機関でのITサポートAI導入による対応時間の劇的短縮や、製造業でのAI予知保全によるダウンタイム削減など、実例に基づく発表があり、参加者の共感を集めました。
また、ザヴェリ氏の基調講演中には、最新のリサーチ結果も共有されました。ServiceNowと教育企業Pearsonが共同で行った調査によれば、「エージェント型AI(agentic AI)により2030年までに各国で大幅な労働力変革が起きる」とのことです。例えば、AIによる労働生産性の向上度合いは国別に見るとドイツで27%、米国で36%、インドでは95%にも達する予測が示されました。これは各国におけるAI活用の進展度合いの差を表していますが、総じて世界的にAI人材の需要が急増し、継続的なスキルアップが不可欠となることを意味しています。
| 地域 | AI活用による成長予測 |
|---|---|
| ドイツ | +27% |
| アメリカ | +36% |
| インド | +95% |
イベント期間中は、基調講演以外にも数多くの注目セッションが開催されました。特筆すべきプログラムとして、今年新たに設けられた「Lead Boldly」という女性リーダーシップ支援プログラムがあります。ServiceNow CFOのジーナ・マスタントゥオノ氏やChief People & AI Enablement Officerのジャッキー・キャニー氏といった社内幹部に加え、Deloitte USの会長ララ・アブラッシュ氏、五輪金メダリストで起業家のアリソン・フェリックス氏、WNBAレジェンドのダイアナ・トーラジ氏といった各界の女性リーダーがステージで対談しました(5月7日開催)。多様な視点から「大胆に率いる(Lead Boldly)」ための知見が共有され、参加者から大きな反響を呼びました。
開発者コミュニティ向けには、例年通り「CreatorCon(クリエイターコン)」がKnowledge内で併催されました。ServiceNowプラットフォームの新米から上級者まで集い、ハンズオンのワークショップや専門家による技術セッションが実施されました。今年は遊び心溢れる企画として、来場者がAI生成アバター付きの「コミュニティトレーディングカード」を作成し交換できるブースも設置されました。自分のスキルセットやキャリアをカード化して他の開発者と交換するというもので、会場は大いに盛り上がりました。

Knowledge 2025 Expo会場の一幕。スポンサーやパートナーのブースが並び、来場者同士や担当者との活発な情報交換が行われた。
イベントの心臓部とも言えるExpo(展示エリア)には、160以上のスポンサー企業やパートナーがブースを構え、最新のAIソリューションやデモ展示を行いました。特に「AI Agent Hub」と名付けられたServiceNowの体験ブースでは、同社プラットフォーム上でAIエージェントがどのように動作するかを実際に体験でき、多くの参加者が列をなす人気となりました。また、Expo内のミニシアターでは業界別セッションが随時行われ、製造業におけるAI活用や金融サービス分野でのデジタルワークフロー事例など、専門的なテーマにも触れられる構成でした。
夜には社交イベントも開催され、5月6日夜のウェルカムレセプションでは音楽や軽食を楽しみながら参加者同士が親睦を深めました。最終日5月8日の夜には、ラスベガスの最先端会場「Sphere」にて豪華アフターパーティが行われ、なんとグラミー賞受賞アーティスト2組によるスペシャルコンサートが催されました。このサプライズ演出に会場は大熱狂し、Knowledge 2025の有終の美を飾りました。
以下に、Knowledge 2025の主な日程とハイライトをまとめます。
| 日程 | 主なプログラム・ハイライト |
|---|---|
| 5月6日 (Day 1) | オープニング基調講演(ビル・マクダーモット氏、特別ゲスト:ジェンスン・フアン氏 他)。新AIプラットフォーム発表。各種ブレイクアウトセッション開始。夕方にウェルカムレセプション開催。 |
| 5月7日 (Day 2) | 2日目基調講演(アミット・ザヴェリ氏、顧客事例紹介)。女性リーダーシップ「Lead Boldly」セッション(ジーナ氏、アリソン・フェリックス氏 他)。CreatorCon開発者イベント終日開催。Expo展示・スポンサーセッション継続。 |
| 5月8日 (Day 3) | 閉幕セッション(将来展望や3日間のまとめ)。認定試験センター最終日。午後に一部セッション終了後、夜にアフターパーティ(Sphereにて特別コンサート)。 |
「Day2基調講演、生デモ連発で圧巻…AIでここまで出来るとは! #Know25 #AI 😲」 – Xより
Knowledge 2025の3日間を通じて、参加者たちは最新技術の知見だけでなく、業界の仲間とのネットワーキングや交流も深めることができました。特に今年はCOVID-19パンデミック以降で最大規模の対面イベントとなったこともあり、直接顔を合わせて議論できる貴重さを再認識する声も多く聞かれました。「現場の生の声を共有し合うことで、新しい発想やビジネス連携のアイデアが生まれた」という参加者のコメントもあり、Knowledgeならではのコミュニティの力が感じられるイベントとなりました。
業界分析:AI時代におけるServiceNowの戦略と位置付け
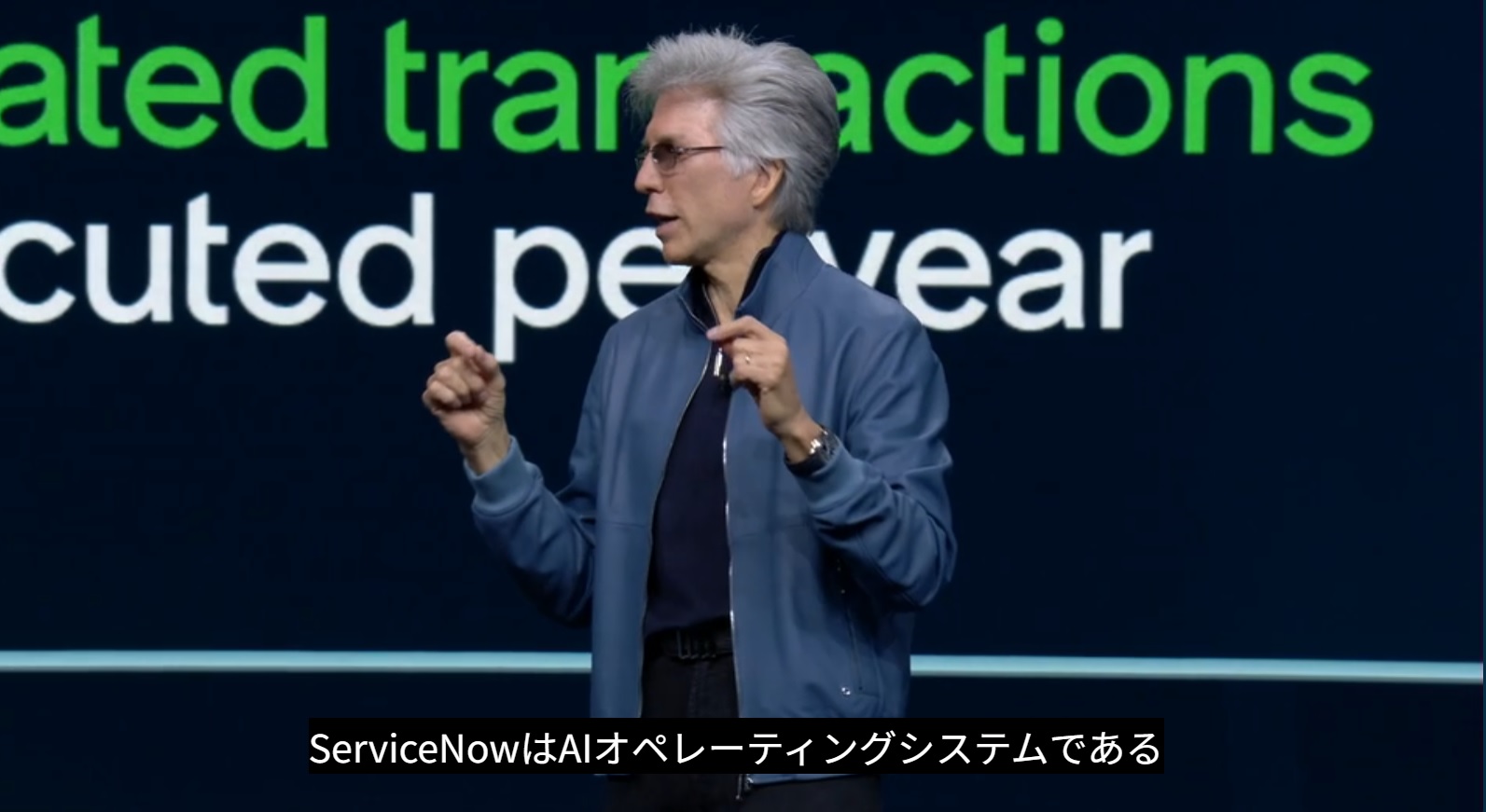
「ServiceNowはAIオペレーティングシステムである」
Knowledge 2025で示された方向性から、ServiceNowが現在どのような戦略で業界をリードしようとしているかが見えてきます。大きなポイントは、「ServiceNowがITサービス管理ツールから、企業全体のAIプラットフォームへと脱皮を図っている」という点です。
ServiceNowは元々、IT部門のチケット管理やワークフロー効率化ツールとして成功してきました。しかし昨今、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)ニーズが高まる中で、自社の強みであるワークフロー自動化を他部門(カスタマーサービス、HR、財務など)にも広げ、さらにAI技術を掛け合わせることで、エンタープライズソフトウェア市場における存在感を飛躍的に高めています。
特に注目すべきは、CRM分野への本格進出です。CRMと言えばSalesforce社が長年市場を牽引してきましたが、ServiceNowは「営業支援に留まらない統合型CRM」と「AI活用による次世代体験」を武器に、顧客管理市場でシェア拡大を狙っています。SalesforceのCEOであるマーク・ベニオフ氏が昨年末のTVインタビューで「ServiceNowはマクドナルドに対するウィンナーシュニッツェル程度だよ」と冗談交じりに牽制したエピソードも知られていますが、それだけSalesforce側もServiceNowの動向に神経を尖らせている証拠とも言えるでしょう。
こうした競争環境の中、ServiceNowが強調しているキーワードが「Agentic Era(エージェントの時代)」です。これはAIの進化の中で、単なるルールベース(第1の波)、単なる会話生成AI(第2の波)を越えて、自律的に目標達成のため行動するAI(エージェント)が主役となる第3の波に入ったという考え方です。ServiceNowはこの「エージェント時代」に対応するプラットフォームをいち早く提示し、企業のAI活用を包括支援する立場を築こうとしています。先述のAIエージェントファブリックやAIコントロールタワーは、その戦略を具現化する重要なコンポーネントです。他社が個別のAI機能を提供する中、ServiceNowは「あらゆるAIを繋ぎ、統制し、実業務につなげる」という統合アプローチで差別化を図っているのです。
さらに、ServiceNowが成功してきた「プラットフォーム戦略」も引き続き強みとなっています。ServiceNowは自社のNow Platform上で自社製品だけでなくパートナーのアプリやお客様自身が開発するアプリを動かせるエコシステムを構築してきました。今回のKnowledgeでは、このプラットフォームにAIの要素を組み込み、例えばServiceNowストアで外部AIエージェント連携のプラグインを提供したり、RaptorDBなど高速データベースとのネイティブ接続を可能にしたりと、プラットフォームの拡張性がさらに打ち出されました。エンタープライズITにおける「ワンストップ基盤」として、ServiceNowは他ベンダーとの連携を積極的に取り込みつつ自社の価値を高める戦略です。
AI時代においては、技術革新の速さにどう対応するかも重要です。ServiceNowは自社研究部門や大学との提携を通じてAI研究を進めており、最新技術を自社製品に素早く取り込む体制を整えています。NVIDIAとの協業もその一環であり、最新GPUによるAI性能向上や新モデル開発を進めています。大企業向けにはガバナンスや透明性(Responsible AI)の確保が欠かせませんが、ServiceNowは統合ガバナンス機能やGRCとの連携で「安心して使えるAI」を売りにしています。
「ServiceNowがAI時代のOS(基本ソフト)を狙ってる感ある。従来の単品アプリは淘汰されるかも… #DX #AgenticEra」 – Xより
総合すると、Knowledge 2025で見えたServiceNowの立ち位置は、「企業向けAIのオペレーティングシステム的存在」になろうとしている、ということです。従来のように部門ごとに別々のシステムやツールを使うのではなく、ServiceNowという共通プラットフォーム上でAIを中心に業務を回す未来像を描いています。他社もAI統合の重要性は認識しており、MicrosoftはMicrosoft 365 Copilotで生産性アプリにAIを埋め込み、SalesforceはEinstein GPTやSlack統合で対抗するなど動きがありますが、ServiceNowはITSM発祥という背景から企業内の基幹系ワークフローに強く、差別化されたポジションを築いていると言えるでしょう。
今後、エンタープライズソフトウェア業界では「どのプラットフォームがAI時代のデファクトスタンダードになるか」を巡る競争が一段と激化しそうです。ServiceNowは今回のイベントで大きく先手を打った形であり、このリードを維持できるか注目されます。
ロードマップ:発表内容から見る今後の展望
Knowledge 2025 で示された新機能や戦略を踏まえ、ServiceNow の今後のロードマップについて整理してみましょう。
- 直近(2025年内)のリリース計画:最新ファミリーは 「Yokohama」(2025年3月一般提供開始)です。AI Control Tower や Now Assist 拡張など今回の Knowledge で紹介された機能の多くは、この Yokohama 版に組み込まれています。また AI Agent Fabric は現在一部顧客で早期導入が進んでおり、正式 GA は 2025 年第 3 四半期を予定しています。NVIDIA と共同開発した新 LLM「Apriel Nemotron 15B」も 2025 年 Q2 中に利用可能になる見込みです。
- 半年〜1 年後(2025 年後半〜 2026 年初頭):次のファミリーリリースは 「Zurich」(仮称)で、2025 年 Q4 公開が予定されています。Zurich では Yokohama で導入された AI エージェント群をさらに強化し、業界別ソリューション(金融・製造・公共など)への深い組み込みが行われると予想されます。なお、従来 Roadmap にあった Washington D.C.(2024 Q1)と Xanadu(2024 Q3)は既に提供済みであり、Zurich はYokohama の次世代という位置づけになります。
- 中長期(2026 年以降)の展望:ServiceNow は「2026 年までに 300 万人の学習者を支援する」という目標を掲げ、ServiceNow University を中心に人材開発を加速します。技術面ではエージェント型 AI の高度化(より複雑な意思決定・対話)、業界特化 AI、さらには量子コンピューティングやフォグ/エッジ AI との連携も視野に入れていると公言しています。加えて、主要クラウド・SI パートナーとのジョイントソリューションを拡大し、企業が「プラットフォーム+サービス+人材」をワンストップで調達できる体制を整える方針です。
- 次回イベント:早くも 「Knowledge 2026」 が 2026 年 5 月 5 日〜 7 日の日程で告知されています。Zurich に実装される新機能の深掘りや、AI エージェントの実運用事例の共有が行われる見込みです。
Yokohama → Zurich へと続くロードマップ全体を通して言えるのは、ServiceNow が 「企業向け AI オペレーティングシステム」 になるという大胆なビジョンを確実に実装し続けている点です。リリースごとに機能が追加されるだけでなく、ガバナンスや学習環境も段階的に整備されているため、企業は安心して段階的に AI を本番活用へ拡大できます。
「Knowledge 2025を経て、ServiceNowの“次”がますます楽しみになった!来年のKnowledge 2026では何が飛び出すか…今から待ち遠しい👀」 – Xより
活用のヒント:ServiceNow新機能を現場で活かすには
最後に、今回のKnowledge 2025で得られた知見を踏まえて、企業のIT担当者が新機能を活用していくためのヒントをいくつか紹介します。ServiceNow初心者の方にも役立つポイントをまとめました。

- オンデマンド配信で最新情報をキャッチアップ: イベントに参加できなかった方も、ServiceNow公式サイトで基調講演や注目セッションの録画を視聴できます。「Best of Knowledge」と題したオンデマンドコンテンツには、AIエージェントのデモや業種別のディスカッションなど見どころが詰まっています。まずはこれらを社内で共有し、経営層や関係部門にも最新トレンドを知ってもらいましょう。
- ServiceNow Universityでスキルアップ: Knowledge会場でも発表された新ラーニングプログラム「ServiceNow University」を活用しましょう。これは従来の「Now Learning」を発展させたもので、AI時代に対応した役割別の学習ジャーニーが用意されています。例えば「AIエージェント開発者コース」や「統合プラットフォーム管理者コース」など、目的に応じたオンライン教材やハンズオンが提供されています。**ServiceNow Universityは基本的に無料で利用可能**で、あなたの習熟度に合わせてカリキュラムがカスタマイズされます。また、Knowledge期間中には認定資格試験が30%オフで実施されるなど、学習者支援も充実しています。ぜひこの機会に認定資格の取得も検討してみてください。
- スモールスタートでAI導入: 新しいAI機能に興味があっても、いきなり全社適用はハードルが高いもの。まずは効果が分かりやすいユースケースから小さく始めることをお勧めします。例えば、ITサポート部門でAI仮想エージェントによるFAQ対応を試験導入してみる、顧客サービス部門で一部問い合わせに対しAIによる自動分類を行ってみる、といった具合です。Knowledge登壇企業の事例でも、最初は限定範囲からスタートし、効果測定の結果をもとに徐々に拡大した例が紹介されていました。PoC(概念実証)を短期間で回し、成功体験を積み重ねるのがコツです。
- 社内啓蒙とガバナンス整備: AI導入を進める際は、技術チームだけでなくビジネス側の理解と協力も不可欠です。Knowledgeで紹介された顧客企業の多くは、現場部門との密な連携によりAIプロジェクトを推進していました。例えば、カスタマーサポートの担当者を巻き込んで応対フローを最適化し、その上でAIエージェントを組み込むアプローチなどです。また、ガバナンス面では社内のAI利用ポリシーを策定し、AI Control Towerのような統制ツールを活用してリスク管理を行いましょう。コンプライアンス部門とも協力し、AIの判断プロセスの説明責任(Explainability)やデータのプライバシー保護など、倫理的な配慮も忘れずに。
- コミュニティで情報収集: ServiceNowはユーザーコミュニティが非常に活発です。Knowledgeイベント自体が大きなコミュニティの祭典ですが、日常的にもオンラインのServiceNowコミュニティサイトや各国のユーザーグループ(SNUG: ServiceNow User Group)で情報交換が行われています。困った時は質問を投稿すれば有志やServiceNow社員が回答してくれることも多く、製品の使いこなしに役立ちます。また、Knowledgeで知り合った業界仲間とはぜひ今後も連絡を取り、お互いの導入状況や課題を共有すると良いでしょう。ある参加者は「隣に座った他社の方から社内展開の進め方で貴重なヒントをもらえた」と話していました。
「さっそく社内検証環境でAIエージェント動かしてみた。思ったより簡単にセットアップできて感動! #ServiceNow #AI」 – Xより
以上のようなポイントを押さえつつ、まずは身近なところからServiceNowの新機能を試してみることが大切です。ServiceNowは「Now Platform」という名前が示す通り、「今この瞬間」から価値を発揮できるプラットフォームを目指しています。ぜひ社内のチームと協力して、小さな成功体験を積み重ねながら、AI時代の業務改革を前進させてください。
まとめ:Knowledge 2025を経て未来へ & 次回予告
ServiceNow Knowledge 2025は、「AIが主役となる企業ITの未来像」を具体的な形で示したイベントでした。導入部分で触れたように、AIを活用した自動化・効率化はもはや避けて通れない潮流であり、ServiceNowはその波に乗るどころか先頭に立って道筋を示そうとしています。新発表されたAIプラットフォームとエージェント群は、決して魔法のような絵空事ではなく、着実に提供時期や適用方法が計画された実践的なソリューションです。
ITに馴染みの薄い方でも、本記事で紹介したポイントを押さえていただければ、ServiceNowが描くAI時代のビジョンと、それが自社にもたらしうる価値の一端をご理解いただけたのではないでしょうか。重要なのは、テクノロジー自体よりもそれを人がどう活かすかです。ServiceNowは「プラットフォーム」「エコシステム」「学習」という三位一体のアプローチで、人とAIの協働を支援しようとしています。これは多くの企業にとって心強い後押しとなるでしょう。
Knowledge 2025の熱気冷めやらぬ中、既に次の戦いは始まっています。他社もAI分野で次々と新戦略を打ち出す中、ServiceNowがこのリードを維持し発展させていくことができるか、引き続き注目が集まります。来年のKnowledge 2026では、今年の成果を踏まえさらに進化した姿を見せてくれることでしょう。
次回の記事では、Knowledge会場で公開された「ServiceNow University」の体験レポートをお届けする予定です。実際にどのような学習コンテンツが提供され、どんなスキルを身につけたのか、詳しくご紹介します。学びの場として進化するServiceNow Universityの全貌に迫りますので、ぜひお楽しみに!